【留学NEXT】応援コメント〈講師の皆さん〉
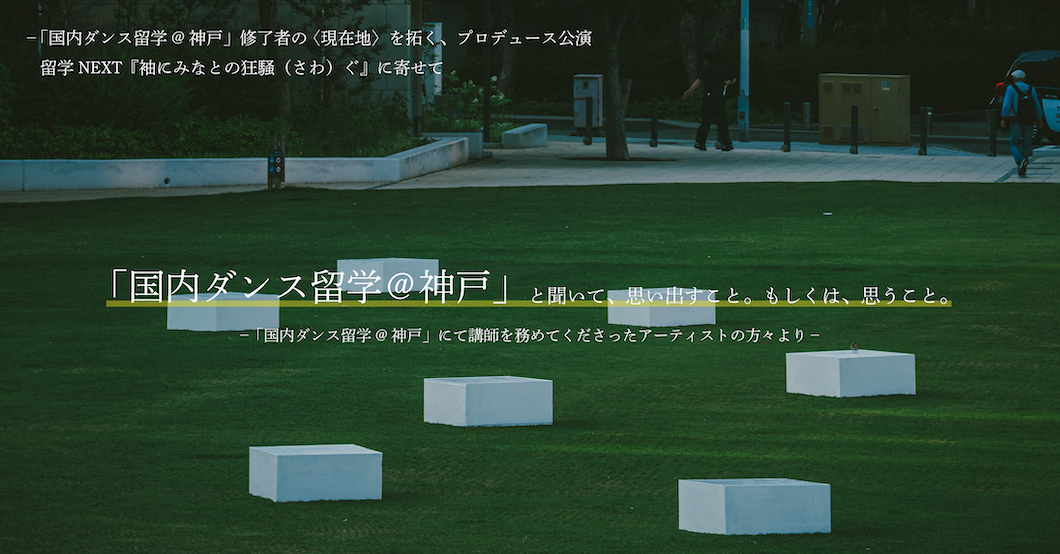
「国内ダンス留学@神戸」修了者の “現在地” を拓く、プロデュース公演〈留学NEXT〉。
修了者の中から9名のアーティストが、新作ダンス作品『袖にみなとの狂騒ぐ』を制作し、7月25日・26日に上演します。
修了者はのべ98名にのぼり、国内外の第一線で活躍している講師陣、関係者の皆さま、そして地域の方々と、数多くの方々の支えによって成り立っている「国内ダンス留学@神戸」。その間に3年間のブランクはありましたが、10年間にわたり継続してきました。
〈留学NEXT〉公演を迎えるにあたって、講師の皆さん、地域の皆さんから多くのコメントをいただきました。このページは講師陣のコメント集です。講師の皆さまの眼差しから、DANCE BOXも知らない「国内ダンス留学@神戸」の姿も見えてきます。(地域の皆さまからのコメントは、7月10日に公開いたします!)
応援コメントと併せて公演『袖にみなとの狂騒ぐ』をお楽しみください!
公演情報はこちら:留学NEXT『袖にみなとの狂騒(さわ)ぐ』
※6月30日時点で集まったコメントを執筆してくださった方の和音順で掲載しています。
6月30日以降に届いたコメントは到着順でご紹介します。
青木尚哉さん(10期/特別ワークショップ講師)
セレノグラフィカ 阿比留修一さん(2期、3期、4期、7期、8期/特別ワークショップ講師)
岩淵多喜子さん(1期、2期、3期、4期、7期、8期/特別ワークショップ講師)
岡田利規さん(3期、4期、7期、8期 / 特別ワークショップ講師)
岡元ひかるさん(9期/特別講師)
鞍掛綾子さん(1期、2期、3期、4期、7期、8期、9期、10期/ワークショップ講師)
児玉北斗さん(7期、8期、9期、10期/特別ワークショップ講師、メンター)
渋谷陽菜さん(7期、8期、9期、10期/ヨガ 講師)
セレノグラフィカ 隅地茉歩さん(2期、3期、4期、5期、6期、7期、8期/特別ワークショップ講師、メンター)
竹田真理さん(3期、5期、7期、8期、9期/ダンス批評、特別ワークショップ講師 等)
寺田みさこさん(5期、6期、7期、8期/Newcomer Showcase振付、特別ワークショップ講師)
永山春菜さん(凱風館)(7期、8期、9期、10期 / 合気道 講師)
Monochrome Circus 森裕子さん(3期、4期、7期/特別ワークショップ講師、8期 / Newcomer Showcase 振付)
山崎広太さん(5期、6期 / Newcomer Showcase 振付)
余越保子さん(5期、6期、8期/Newcomer Showcase 振付、講師、メンター、7期統括ディレクター)
湯浅永麻さん(8期、9期/特別ワークショップ講師)
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
青木尚哉さん (10期/ 特別ワークショップ講師)
新長田という街を少し歩くと、その異常な可笑しさに気がつく。有名な巨大モニュメントもそうだけど、何故か逆さ文字の電光掲示板だったり、喫茶店のモーニングの選べるドリンクがビール2杯だったりと、正気と狂気がいりまじっていて、そんな街にダンスボックスは割とひっそりとある。(ひっそりというのは馴染みまくっているという意味かもしれない)そこからダンス業界には類をみない企画を次々と打ち出し展開、中でも秀一なのが国内ダンス留学だと思う。自分の枠を知るにも、広げるにも、突き破るにも、もってこいの環境ではないだろうか。ここを通過したものたちの祭典。きっと観るものの期待と想像をさらりと裏切るものになるだろう。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
セレノグラフィカ
阿比留修一さん (2期、3期、4期、7期、8期/特別ワークショップ講師)
国内ダンス留学の10期という継続にまず敬意を評します。
皆さんそれぞれがどうやって、ダンスに出会ったのか?なぜ留学に飛び込んでまでダンスを深く追求するのか?誰もが誰とも違う動機を持っています。その動機は、踊り続けている人は、私も含めてもれなく持っています。
人は必ず歳を重ねていき、身体も変化していきます。その変化もみんな違う。留学生だったあの頃とは違う今を、まだ見ぬ未来を、一人一人の今の身体で精一杯踊ってくれるに違いない今回の作品に期待しています。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
岩淵多喜子さん(1期、2期、3期、4期、7期、8期/特別ワークショップ講師)
「国内ダンス留学@神戸」は、若手ダンサーや振付家、そしてそれを志す方々が身体と表現に真摯に向き合い、濃密な時間を重ねる場。私自身も、受講者やスタッフの皆さんの熱意や柔軟な発想、真摯な姿勢に触れるたび大きな刺激を受けてきました。修了者の皆さんがここで培ったものを糧に、各地でしなやかに活動されている姿に、積み重ねの大切さと無限の逞しさを感じます。今年、“留学NEXT”として修了者9名によるプロデュース公演『袖にみなとの狂騒(さわ)ぐ』を上演されるとのこと、心からお祝い申し上げます。過去を振り返りながら未来へと踏み出すこの新たな試みに、心からエールを送ります!
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
岡田利規さん (3期、4期、7期、8期 / 特別ワークショップ講師)
演劇という、ダンスとそれなりに近い関係があるとはいえるだろうが決してダンスではない形式を主にやってる作り手として、ぼくは、ダンスは羨ましいです。その一方で、こうも思う。ダンスすることって、なにもそれを「作品」にせずとも、それじたいでめちゃめちゃ成立している行為だ。だからダンス「作品」をつくるのって、すごく難しいんじゃないかな、と。なぜダンスをするだけではなく、ダンス「作品」をつくりたいのか。それがガツンと来る感じでわかるダンス「作品」を体験したとき、ぼくはいつも鳥肌が立ちます。そういうものつくってほしいです!
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
岡元ひかるさん (9期/特別講師)
「国内ダンス留学@神戸」についてまず思い出すのは、この企画が始まった年のことです。当時ダンスを自分でも踊っていた私は、いろいろな事情でこの留学に応募することは断念したけれど、プログラムに単発で参加させて頂くなかで、一期生のダンサーやスタッフの方々と知り合いました。どんな形で関わるにしても神戸でダンスを学びたい者を拒まない、オープンかつどこかサバサバ(笑)した空気に助けられ、普通の大学では決して学べないことを学ばせて頂きました。
だから卒業生の方々の輝かしい活躍を目にするといつも、きっとホームのような存在があるからこそ遠くまで飛んでいけるのだろうなあ、と感じます。私個人にとっては、この約10年間は、神戸という土地で研究を続けた孤独な時期と重なりますが、新長田に行けば新鮮な風に当たれると知っていることが一つの心の支えでした。「国内ダンス留学」にはこれからも新しい風がどんどん吹いて、この世界でサバイブする力を、ダンスと共に生きていきたい人に与え続けてくれるのだろうなと思います。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
鞍掛綾子さん (1期、2期、3期、4期、7期、8期、9期、10期/ワークショップ講師)
国内ダンス留学@神戸、11期に突入!1期からこの留学生に関わらせていただき、こんなに長くご一緒できるとは思っておりませんでした。そしてこの留学卒業生が、それぞれこんなに活躍するとは。。。この年月が築いたものは、単なる功績ではなく、神戸から全国へ放たれた新風となって輝いています。これからもたくさんの人と出会い進んでいくと思いますが、なかなか信頼できる出会いは少ないもの。この同じdbで学んだ絆と信頼を武器に、安心してこれからも大海原に旅立ってください。こうして集まる機会を作ってくださるdbスタッフの愛に包まれて、これからもその活動の波を起こす人材であることを期待します。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
児玉北斗さん (7期、8期、9期、10期/特別ワークショップ講師、メンター)
「国内ダンス留学@神戸」で講師をさせてもらって、もう4年目になります。
今まで出会ってきた受講生のみなさんは、例外なく強い意志を持つアーティストたちばかりでした。新長田での生活は、ダンスと向き合うだけじゃなく、自分の生き方と真剣に向き合う時間なのだろうと思うし、そうやって毎日を過ごしているみんなに置いていかれないよう、僕自身もピリッとした気持ちになります。
振り返れば僕自身、4年前はまだまだ未熟だったなあと思いますが、ここで毎年新たな刺激をもらって少しづつ前に進むことができています。日本で1番、真剣にダンスと向き合っている人同士が出会える場所なんじゃないかな?と冗談抜きに思っています。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
渋谷陽菜さん (7期、8期、9期、10期/ヨガ 講師)
約8ヶ月の間、踊りに集中できる環境に身を置き、一日中続くクラスやリハーサル。様々な状態で朝のレギュラークラスにやってくるダンサー達が、クラスを受講した後に、何かが切り替わったかのようにスッと立ち上がって黙々と踊りを作る姿が、この国内ダンス留学の日常の風景であり、一番印象に残っている姿です。
そういった、精神と肉体が何かをポロッと脱ぎ捨ててまた踊りに向かっていくのが、シンプルで清々しく、力強いなと感じていました。今回、これまでの修了生9名が集まり、一つの作品を作れることは、このプログラムを経てきた人間にしかわからない感覚を共有しながらも、新しい挑戦ができる素晴らしい機会だと思っています。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
セレノグラフィカ
隅地茉歩さん (2期、3期、4期、5期、6期、7期、8期/特別ワークショップ講師、メンター)
講師として関わらせて頂いていた後も、「国内ダンス留学@神戸」はずっと気になる存在である。自分自身がダンスボックスに育ててもらった感覚があるからだと思う。勝手ながら、他人事では無いのだ。創る、踊る、観る。その場がいつもそこにあって、そこにいつもダンスをこよなく愛する仲間やスタッフがいて、泣きつ笑いつ暮らし丸ごとの8ヶ月は、確実にその後の活動を続けていくに当たっての羅針盤となっていることだろう。譲れないことにどこまで食い下がるのか、心底揺さぶられるものにどれだけ正直でいられるか。ちょっとやそっとで語り尽くせないあれもこれも、今回の『袖にみなとの狂騒(さわ)ぐ』に注ぎ込んでくれる9人のメンバーがいると言う。10期を終えた節目に何と楽しみなことか。気が早いけれど、おめでとうございます!
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
竹田真理さん (3期、5期、7期、8期、9期/ダンス批評、特別ワークショップ講師 等)
舞台芸術の最前線へ、あるいは各地域のコミュニティへ、種子がはじけるように飛び散っていった国内ダンス留学@神戸の修了者たちが10期分の蓄積のもとに集結!こういう日がいつか来る気がしていた。誰にも覚えがあると思うが、共に何かを学んだ経験は人生において特別だ。師弟関係とも、振付家とダンサーとの実利的な関係とも違った、同胞との、振り付け/振り付けられる水平な関係。切磋琢磨というよりはもう少し親密な、研鑽と探求と試行錯誤と自由闊達なやりとりの様子を、近からず遠からずの距離で10年にわたって見てきた。毎年の成果上演も、その後の活躍についても然り。共に学び合った経験が、彼女や彼らの現在があるそれぞれの場所で、ダンスを人生の中心に置く生き方を選択させ続けている。大袈裟でなく日本のダンスにとっての希望だと思う。新たに新長田に集う、とびきりの強者(つわもの)ぞろいの競演/共演/饗宴に、期待は膨らむばかりだ。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
寺田みさこさん(5期、6期、7期、8期/Newcomer Showcase振付、特別ワークショップ講師)
この数十年、各地で数多くのダンス育成プログラムが展開されていますが、私の知る限り、この国内ダンス留学はかなり特別なプログラムだと思います。そしてその成果は修了者たちの現在の活躍が明確に物語っています。私は2度クリエーションに関わらせてもらいました。一月弱の短期間で発表に至らねばならない過酷なプログラムで、当初は連日ビッシリ組まれているスケジュールに「保つのか私?」と怯みましたが、実際には毎日時間を惜しみながら稽古を終える日々で、それはそれは密度の高い充実した時間でした。とはいえ私にとってはほんの一月、しかし参加者はそれを年間通して継続するわけですから、かなり凄まじい体験だと思います。思うに修了者たちは、普通に考えると1年弱ではとても消化しきれない内容を、ぎゅーっと圧縮して体内に保存し、その後、要所要所で解凍しながら血や肉に変えているのではないでしょうか?その意味でも、このタイミングでの新作発表には大いに期待したいところです。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
永山春菜さん(凱風館)(7期、8期、9期、10期 / 合気道 講師)
国内ダンス留学@神戸には7期より関わらせていただいています。その年ごとに道場で出会う留学生は変わるのですが、共通すると感じることは、それまでの努力による身体能力の高さや身体に対しての新しい気づきに興味を持ち続ける姿勢です。もちろん表面の身体の使い方だけではなく、私たちが大事にしている心の持ち方や呼吸法についても大変興味を持たれるところは同じようです。また、言葉にするという行為をとても大事にされている印象があり、私もいつも見習うところであります。その時間にどんなことをどんなふうにその場にいる皆さんと探求していくか、私自身も立ち返り、考える機会を与えていただいています。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
Monochrome Circus
森裕子さん (3期、4期、7期/特別ワークショップ講師、8期 / Newcomer Showcase 振付)
今回の留学NEXT公演に出演される元国内留学生は、多かれ少なかれどこかで顔を合わせいている方ばかり、それぞれが生活とのバランスをとりながらアーティストとしての活動を続けているということを、とても嬉しく思います。新長田の国内留学での時間が、彼らのサバイバル能力を育んだのでしょう。
年月を経て、それぞれ別の土地で経験してきたことがどのように作品に反映されるのか楽しみにしています。
私自身の新長田の思い出は、dbへ向かうショッピングアーケードを歩きながらの人間観察。路地裏探索。寿荘でのまったりとした時間。ラビット・ハウスの生活音。あぐろの湯(特に壺湯)。須磨海岸へのサイクリング。牛すじコロッケ。古着屋でのお買い物。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
山崎広太さん (5期、6期 / Newcomer Showcase 振付)
その頃の私にとって、日本でダンスアーティストたちと創作することは、
干上がった日々にふいに差し込んだ、ひとすじの潮風のようなプログラムでした。
私は水辺が好きで、須磨の海岸に通うのが日課になっていました。
朝の光のなかを走ったり、潮の匂いをまといながら糸を垂らしたり——
それから、ゆっくりとリハーサルやワークショップへ向かうのです。
長田という土地にいると、自分がまるで「ダンスの漁師」になったような心地がして、
胸の奥から、野生の匂いが立ち上ってくるのを感じていました。
それはきっと、さまざまな国からの留学生や、多様な人種が暮らすこの街の、
混ざりあう風土が、私の感覚の奥深くに触れていたからかもしれません。
年を重ねるごとに、私の身体は、ますます大海原になっていきます。
波間を泳ぐように、潮目を感じ、
ときに、群れのなかを縫うトビウオのように軽やかに、
さまざまな生命の気配とすれ違いながら、
気づけば、踊ることそのものが、
静かに、満ちていく——Joy。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
余越保子さん(5期、6期、8期/Newcomer Showcase 振付、講師、メンター、7期統括ディレクター)
「踊りたい」——その強い思いに、私は深く共感します。
踊っていても、踊っていなくても、心はいつも踊りのことばかり。
踊らなければ、生きている実感が持てない。
その感覚は、本人にしかわからないものかもしれません。
家族や友人にもなかなか理解されず、経済的に報われることも少ない。
けれど、それでも踊り続ける。
そんな“変わり者”は、決して多くはないけれど、確かにここにいます。
そんな“変わり者”のみなさんへ。
留学NEXT 新作ダンス作品『袖にみなとの狂騒(さわ)ぐ』
ダンサーとして歩んできた日々。
その今を、この“静かな狂騒”の中で、どうか見つけてください。
≡ ≡ ≡ ≡ ≡
湯浅永麻さん(8期、9期/特別ワークショップ講師)
近年、様々な国でダンスを教える機会を頂き、海外での若いダンサーや振付家、アーティストが学ぶ場も少しづつ見てきました。そこで思うのは、やはり日本にはそういった場が少ないという事。そんな中で地元の方々からの理解もあるダンスボックスの国内ダンス留学@神戸の企画で、貴重な学ぶ機会を得たアーティスト達が近年様々な活動をして活気を与えている事は、もっと評価されるべきだと思います。私も講師として何度か参加させて頂いて、スタッフの方のアーティスト達を暖かく見守る姿勢や、情熱的に活動を続けていらっしゃる様子に、とても感銘を受けています。
どうかこの企画やダンスボックス自体が、市民や神戸の街から更に支援を受けて、これからも続いていきますようにと願っています。
この記事に登場する人
青木尚哉
振付家/ダンサー。zer◯代表。東京都あきる野市生まれ。幼少期には地元で祭囃子を習い、16歳よりダンスを始める。 noism(04~08) 、JAPON dance project(13~16)の活動を経て、自身主宰のダンスグループzer◯(12~)の立ち上げへと進む中、舞台芸術に定まらず、ダンスそのものの本質を求め活動中。人の身体の形や動きを自然現象と同じように観測する身体感覚メソッド「ポイントワーク」を開発し、劇場以外の社会でも「ダンスの活用」を模索する。音楽、建築、福祉、教育、保育のフィールドで協働を進める。西岡・福谷バレエ団(京都)にてアドバイザー、振付家に就任。
2024年5月22日 時点
阿比留修一
ダンサー。近畿大学文芸学部芸術学科演劇芸能専攻在学中にダンスと出会い、モダンダンスを故神澤和夫氏に学ぶ。「かかとのない男」と恩師に称され、一貫して新しいダンステクニックと身体の在り方を追求し、現在に至る。
1997年隅地茉歩とセレノグラフィカを結成、以後ダンサーとしてほぼ全作品に出演。スタイルの確立と解体を続行し、隅地とともに独自のデュエットを数多く発表。動きの緩急や質感の落差を追求した身体テクニックとダンススタイルで、多くの観客の共感を呼んでいる。近年はセレノグラフィカとして、公演・ワークショップ・アウトリーチ・セミナーなど、対象や方法に限らず、あらゆる要請に応えつつ、全国を駆け巡る。平成8年度大阪府芸術劇場奨励新人(平成10年まで)。
2023年3月25日 時点
岩淵多喜子
ラバンセンターにてコンテンポラリーダンスを学ぶ。エルヴェ・ロブ、テッド・ストッファー等と活動後Dance Theatre LUDENS設立。LUDENSの全作品の演出、構成、振付を行い、国内外で作品を発表、高い評価を得る。また海外のアーティストとの共同製作、人材育成プログラムのプロデュース等、様々な角度からコンテンポラリーダンスの魅力と可能性を追求、発信している。「Be」にて横浜ソロ×デュオコンペティションにて【横浜市文化振興財団賞】、【在日フランス大使館賞】、「Distance」にて【舞踊批評家協会新人賞】受賞。2000-05年公益財団法人セゾン文化財団、芸術創造活動助成を受ける。日本女子体育大学運動科学科舞踊学専攻専任講師。
2023年4月8日 時点
岡田利規
1973年横浜生まれ、熊本在住。演劇作家、小説家、チェルフィッチュ主宰。
2005年『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。主宰する演劇カンパニー・チェルフィッチュでは2007年に同作で海外進出を果たして以降、世界90都市以上で上演。
ミュージシャン、美術家、ラッパーなど、様々な分野のアーティストとの協働を積極的に行い、森山未來、酒井はな、湯浅永麻などダンサーとのコラボレーションも多数。近年では欧州の劇場レパートリー作品やオペラ演出を手がけるなど、活動の幅を広げている。
2007年にはデビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』(新潮社)を発表し、2022年『ブロッコリーレボリューション』(新潮社)で第35回三島由紀夫賞、第64回熊日文学賞を受賞。
2023年4月10日 時点
岡元ひかる
言葉を用いた振付や動きの手法に関する研究を行っている。これまでピナ・バウシュの振付手法やGAGA、土方巽の暗黒舞踏における言語使用に注目してきた。2022年に博士号を取得(学術、神戸大学)。薄井憲二バレエ・コレクション アシスタント・キュレーター、追手門学院大学の非常勤講師、武庫川女子大学研究員を経て、現在、芸術文化観光専門職大学助教。横浜ダンスコレクションEX2014新人振付家部門奨励賞。
https://researchmap.jp/hikaruokamoto
2023年5月13日 時点
鞍掛綾子
1998年~2009年NY在住 2001年NY州立PurchaseCollege 舞台芸術学科舞踊専攻大学院卒業 MFA修得(Master of Fine Arts)。 1999年〜2004年スペインの国際振付コンクール(https://www.cicbuny.com/)の立ち上げ、審査員を務め、2021年よりWS講師、審査員メンバーとして招聘、現在に至る。NYだけでなく世界の若手振付家の発掘を目的にReverb Dance FestivalをNYで2005年に立ち上げる。2006年Gaga Japan設立、日本でGagaを広めるWSなどの開催を始める。神戸女学院大学舞踊科非常勤講師、京都女子大学非常勤講師、武庫川女子大学ダンス部外部コーチ
2025年5月11日 時点
児玉北斗
2001年より2019年までダンサーとして北米や欧州で活動。ヨーテボリオペラ・ダンスカンパニー、スウェーデン王立バレエなどに所属しマッツ・エックら国際的な振付家の作品にて主要なパートを務める。2018年にはストックホルム芸術大学修士課程(振付)を修了し、近年の振付作品は『Trace(s)』(2017)、『Pure Core』(2020)などがある。2022年より現在に至るまでは、民俗学における「をどり」概念を参考にして、不安に抗する祈りとして地面を押し続けるパフォーマンス『Wound and Ground』を豊橋や京都を始め各地で上演し、その都度新たなヴァージョンとして更新し続けている。現在は芸術文化観光専門職大学准教授としてダンス教育ならびに美学研究にも従事している。www.hokutokodama.com
2025年5月11日 時点
渋谷陽菜
新潟県出身。ダンサー、ヨガ講師として関西を中心に活動。2019年、余越保子 構成/演出/映像/監修「shuffleyamamba」各地公演に共同振付、出演。香川県拠点のダンスユニットEclogionを主宰し、2021年「Dilemma」を振付/出演。JCDN主催、コミュニティダンスファシリテーター養成スクール応用コース修了。Be+yoga Academy teachertraining修了。
2023年4月28日 時点
隅地茉歩
セレノグラフィカ代表。同志社大学大学院文学研究科修了。高校の国語教師在職中にダンスと出会い、その後関西を拠点に国内外でダンサーとしての研鑽を積む。1997年阿比留修一とカンパニーを結成、阿比留と共に「身体と心に届くダンス」を追求。自身も出演するデュエット作品の創作を基軸に、ソロやグループの創作も手がけ、近年カンパニー外へも作品を提供。振付家としては繊細で大胆かつ不思議で愉快な作風、ダンサーとしては緻密な身体操作によるワンダームーブメントが持ち味。ワークショップやアウトリーチのファシリテーターとしての経験値も高い。
TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD2005にて、グランプリに当たる「次代を担う振付家賞」受賞。2021年『身体のことば〜振付家の視点から〜』刊行。2014年より京都精華大学非常勤講師。
2023年3月25日 時点
セレノグラフィカ
(隅地茉歩、阿比留修一)
Selenographica は、Selenography(月面地理学)+ica で「月究学派」(時間や場所によって変化する月のように捉えどころのないもの=ダンスを追求する者たち)の意。1997年、隅地茉歩と阿比留修一によって結成。多様な解釈を誘発する作風と、緻密な身体操作が持ち味。隅地茉歩(TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2005「次代を担う振付家賞」[グランプリ]受賞)は「踊るぬいぐるみ」、阿比留修一(平成8年度大阪府芸術劇場奨励新人認定)は「かかとの無い男」と称され、リヨンダンスビエンナーレ(仏)、パリ日本文化会館(仏)、 ダンスアンブレラ(英)、インターナショナルサマ―ダンスフェスティバル(韓国)、アートレイジフェスティバル(オーストラリア)など国外でも作品を発表、「物語から抜け出した老いた子供」(ル・モンド紙)などと評された。近年は、公演、ワークショップを含め国内各地へ遠征を重ね、多数の市民参加作品の創作や教育機関へのアウトリーチも積極的に行い、ダンスの多様な発信に注力する。また、他ジャンルのアーティストとのコラボレーションの機会も多く、身体の動きによるアプローチの可能性について探究を続けている。(一財)地域創造「公共ホール現代ダンス活性化支援事業」登録アーティスト。http://selenographica.net/

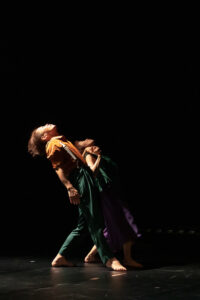
photo Misa Shigematsu
2023年3月28日 時点
竹田真理
東京都出身、神戸市在住、関西を拠点に批評活動を行う。毎日新聞大阪本社版、国際演劇評論家協会日本センター発行「シアターアーツ」ほか一般紙、専門誌、ウエブ媒体等に執筆。ダンスを社会の動向に照らして考察することに力を注ぐ。
2025年5月11日 時点
寺田みさこ
幼少よりバレエを学ぶ。1987年より石井アカデミー・ド・バレエにて、石井潤振付の主要レパートリーに多数主演。1991年より砂連尾理とダンスユニットを結成し国内外で作品を発表。2002年「トヨタ コレオグラフィーアワード2002」にて、次代を担う振付家賞(グランプリ)、オーディエンス賞をダブル受賞。平成16年度京都市芸術文化特別奨励者。2006年以降ソロ活動を開始し、山田せつ子、山下残、白井剛、笠井叡振付作品の他、渡邊守章演出作品などに出演。自身の作品としては、2007年ソロ作品「愛音」@世田谷シアタートラム(独舞シリーズ)/びわ湖ホール(夏のダンスフェスティバル)、2013年グループ作品「アリア」@伊丹AIホール、2018年3人の振付家(マルセロ・エヴェリン/チョン・ヨンドゥ/塚原悠也)によるソロ作品「3部作」@DANCE BOX/横浜ダンスコレクション、等を発表。アカデミックな技法をオリジナリティへと昇華させた解像度の高い踊りに定評がある。また2007年〜2015年まで京都造形芸術大学にて准教授を勤める他、各地でワークショップなどを行い、後進の育成に勤める。
2023年4月7日 時点
永山春菜
2004年に内田樹師範の指導される神戸女学院大学合気道部で合気道に出会う。幼少期より病によって激しい運動は禁止されていたが、この出会いによりどんどん心身の使い方が更新される。卒業後、自身の稽古場として合気道高砂道場を主宰。現在に至るまで高砂、芦屋、神戸住吉で子どもから大人までの指導を中心に活動し、命の力の高め方、使い方を日々研究している。合気道五段。
2023年4月9日 時点
Monochrome Circus(坂本公成+森裕子)
拠点、京都。90年代後半「ダンスの出前」で有名な『収穫祭』シリーズでワールド・デビュー、海外、国内で300回を超える上演を行う。リヨン・ビエンナーレ(仏)、ベイツ・ダンス・フェスティバル(USA)、SI Dance Festival(韓国)、Full Moon Dance Festival(フィンランド)、フェスティバル・ドートンヌ(仏)、瀬戸内国際芸術祭、混浴温泉世界、鳥の芸術祭など国内外で活躍。藤本隆行氏(dumb type)、真鍋大度氏(Rhizomatix)やgrafなどとのコラボレーション作品や、’05年から開始した『掌編ダンス集』という大小の作品群を持つ。2023年度は詩人の和合亮一氏とのコラボレーションや、結成33周年記念公演に取り組む予定。
2023年4月6日 時点
山崎広太
笠井叡、井上博文に師事。07年ニューヨーク・パフォーマンス・アワード・ベッシー賞受賞、12年NEFA財団、12、15年ナショナル・ダンス・プロジェクト助成、13年FCAアワード、17年NYFAフェロー、18年グッゲンハイム・フェロー受賞。Body Arts Laboratory/whenever wherever festival主宰。2021年よりベニントン大学所属。最近はFootnote New Zealand Danceとの協働プロジェクト作品「薄い紙、自律するシナプス、遊牧民、トーキョー(する)」で東京、愛知、ウェリントンで上演。
2025年7月2日 時点
余越保子
舞踊家、振付・演出家、映像作家。広島県出身。
1987年から2014年までダンサー、振付家としてニューヨークとアムステルダムを拠点に活動。ソロパーフォーマンス作品『SHUFFLE』で2004年にアメリカの優れた舞台芸術作品に授与されるベッシー賞を受賞。2003年より日本舞踊の世家真流に入門。日本の古典芸能の身体を基礎としたコンテンポラリーと伝統を巡る国際共同ダンス3部作品を10年に渡りNYにて企画制制作し、ベッシー賞、グッゲンハイム・フェローシップ、ファウンデーション・フォー・コンテンポラリーアートアワードを授与。2015年にNYのダンススペースプロジェクトにて発表された『ZERO ONE』はニューヨークタイムズ 紙の批評家が選ぶ2015年度ベストテンダンスに掲げられた。上記の活動は、ニューヨークのダンスコミュニティにおいて、アジア人の身体性の新しい視点を西欧文化圏に投げかけるきっかけを作った。
2015年より京都に拠点を移す。日本舞踊の身体訓練を継続しつつ、観世流シテ方能楽師の田茂井廣道氏に師事。踊りや舞の古典の型、振付や技法をキネシオロジー(運動学)的視点から解析度を上げるペタゴジィ(教授法、訓練法)、アーカイブ(継承)をダンサーの身体で思考する活動を独自に展開している。舞台制作の他に、映像作家として、黒沢美香、首くくり栲象、川村浪子主演映画「Hangman Takuzo」(余越保子監督)を企画制作。 小山登美夫ギャラリー、シアター・イメージフォーラム(Dance NewAir主催)、神戸映画資料館、Nooderzone Performing Arts Festival(オランダ)などで上映。また、自身が書いたエッセイ集「一生に一度だけの」が森鴎外記念自分史文学賞大賞を受賞(学研出版)するなど創作活動は多岐に渡る。近年は、羽鳥ヨダ嘉郎著『リンチ(戯曲)』の第20回愛知県芸術劇場主催AFF戯曲賞受賞記念公演(2022)の演出・振付を手がけ、2024年度のKYOTO EXPERIMENT京都国際舞台芸術祭に招聘された。
2025年5月12日 時点
湯浅永麻
NDTに11年間所属後フリーとなり、マッツ・エックの 『Juliet&Romeo』ジュリエット役、サシャ・ヴァルツ『Körper』等に客演。シディ・ラルビ・シェルカウイのダンス、 オペラ、演劇作品など多数出演。異ジャンルの様々な著名アーティスト達とコラボレーション作品を発表。第13 回、15回日本ダンスフォーラム賞受賞。近年はダミアン・ジャレx名和晃平『Planet[wanderer]』、『Mirage[transitory]』などに出演。様々な人との対話/交流を試みるnosmosis research を立ち上げるなど、国内外で多岐にわたって活動している。カウンターテクニックティーチャー。
2025年5月17日 時点


