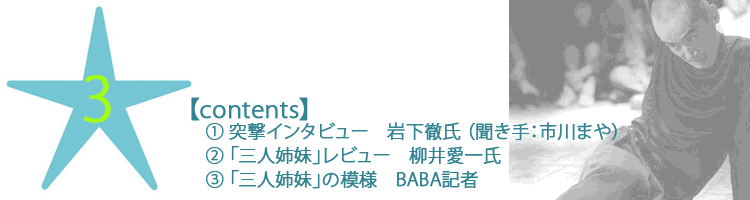(市川) (市川)
今回の「即興セッション」の見所や試みについてお聞かせ下さい。
 (岩下) (岩下)
作品としてではなく、その場で生じる予測できない突発的な出来事、
あらかじめ仕組まれているものは何もない
、という事でやりたいと思います。
予測不能ということにおいては観客の皆さんと演者は対等な立場にたっているという条件なんですね。
その条件をふまえてひとつの場が生まれてきたらいいなと思います。
ですから、作品として見るダンスではなく体感するダンスへと。どんなダンスなんだろうと考えたり解釈を分析しながらみるのではなく、全身、五感、丸ごと全体を感じて頂きたいです。
 (市川) (市川)
3人での顔合わせはいかがでしたか?
 (岩下) (岩下)
実は3人ではまだ会っていないんですね。それぞれとはお会いしたことはあるのですが、、、当日が初の顔お合わせとなります。
 (市川) (市川)
岩下さんにとっての交感(コミュニケーション)とは何ですか?
 (岩下) (岩下)
その場の共有。関係をその場でつくることです。「即興」は、勝手気ままにやっていると思われがちですが、そうではないんです。場のコミュニケーションなんですね。コミュニケーションとは双方向で、一方的に発するだけではないのです。相手が発したものを受け取ったり発展させたりするやりとりが、交感としての即興の根差すところです。
 (市川) (市川)
毎回、黒い衣装ですが、、、(当日も全身黒)何かこだわりとか・・・?
 (岩下) (岩下)
こだわりというか、なじみ深い色なんですね。実はバンドを昔やっていて、その時に黒い服をよく着ていました。今もその延長線上にあるような感覚なんですね。
 (市川) (市川)
・・・!! バンドでは何をされていたんですか?
 (岩下) (岩下)
ベースです。
 (市川) (市川)
以前、私は岩下さんの舞台を観て、その時のアフタートークで「横への関係性」ということについて、おっしゃっていたのですが、詳しく教えて頂けますか?
 (岩下) (岩下)
「縦」というのは権力的な構成を作りやすいのですが、なるべく同じレウ゛ェルを作りたいのです。
舞台というのは、どうしても演者と観客という見えない制度があって、そういう構想ではなく、その境界が曖昧になって、消えてしまえばいいなぁと、、と思います。つまり。それが「横」の関係である、、と。
 (市川) (市川)
最後に、即興の難しさについて語ってもらいました。
 (岩下) (岩下)
何かをしよう、、と考えるのではなく、身体が先行するのが理想ですが、つい止まってしまうと「何かをしなければ」と考えてしまう。その時は、それを止めて、何もする必要が無いのではないかと思うんですね。
またそれが難しいのですが、、、。難しいからこそ放棄したくない、踊れなくなるまでやめたくないんですけどね。
そう、強く静かに、そしてニコッと笑い、「意識は常に定型というワナをしかけてくる」そのワナにはまりたくないんですけどね、、と改めて今回の「即興セッション」への心意気を聞けました。(聞き手/市川まや)
---------------------------------------------------

すーっと流れるような舞台が展開された。いろいろなお楽しみが用意されていたのだけど、そのすべてが自然に一つの物語に収斂されていく、しかも、つねにばらばらになって拡散していくことが意図されている。計算された異物=ぎこちなさの挿入が観る者に却って自然な物語の展開をスムーズに了解させた。勿論この物語というのは「三人姉妹」という古典とはまったく関係のない、三人の女性のダンス・マイム・唄その他がその場、その場で作り上げていく物語なのだ。個人的には、未だにチェーホフの「三人姉妹」というお話はなにが言いたいのかよく理解できない。その分からないところから「作品」を観るというお楽しみが始まるのだと思う、そして、その美味しい所が堪能できた。
三人の精悍なダンスから始まる。ここでは誇張された仕草や、ふざけた仕草もまだ緊張感を伴っている。三つの物語が饒舌な肉体の語りによって展開される。そして突然の中断、一人ずつのおしゃべりはコミュニケーションを図る度に中途半端に途絶える。棄てられた人形の様に奇妙にエロティックに横になったポーズで、強引に始まるであろうエピソードを終わらせる。三人三様の動き、決して意思疎通のできない関係性という、閉じられた「相互の関係性」が見えてくる。漠然とした自らの物語を紡ぎ出す時、その動きは美しい。演出されてはいるのだろうけれど、それを度外視しても踊ることを楽しんでいるダンサーの美しさだ。で、ここで個々の具体的な関係性という野暮な現実がやってくる。くすんだ色のワンピースからはみ出したズロース、そこからはみ出した足。不思議なことに猥褻な印象はなく唯野暮ったい生活が見えてくる。流麗で精悍な部分では成り立たなかった三人のコミュニケーションがここで成立する。追い討ちを掛ける様に「三人姉妹」なんて結局はニートの物語だと切実に唄い語られる。21世紀の現実の問題としての「三人姉妹」。小池博史の「三人姉妹」が見えてくる。退屈で無力な毎日をどう塗布したらいいのか分からないだらしのない生=ズロースのだらしなさ=性の行方。これにはその後の引き締まったSMコスチュームによる反撃が用意されている。鞭が輝き円舞する、綺麗だ。彼女たちは充分に淫靡だ。ラストシーン「働く」「生きましょう」「行きましょう」とチェーホフの台詞が響く、最後の最後に、あらた真生のアッカンベー。「三人の姉妹」の華麗で淫靡で野暮な物語ってなんだったのか、と、楽しく考えさせてくれた。
----------------------------------------------------------------------

【上田美紀】
何が始まるんだろう・・・いつもと違うdB。幕間があり、椅子や食器、そして
電球、マイクまでもが置いてある。早口言葉のような台詞を言いながら3人が
手足を動かす。誰かほんの一瞬でも間違ったら絶対ぶつかるなぁ。
すごいな・・・と思っていたら、SM衣装で電球を振りまわす。
いったいここはどこなのだろう、と思うほど異空間に見えた。
ひとしきり暴れるとおもむろに服を着る。いつの時代も女性はタフだ。あれもこれも
したい、ご飯も食べなきゃ。散らかしたものを片付けてる時間なんてないわ。
次はどうなるのだろう、何をするのだろう、始終わくわくしていた作品だった。
そして、アフタートークで小池さんが日本人が一番理屈っぽい、とおっしゃっていた
のが印象的だった。
【横堀ふみ】
舞台を作っていく時の一番初めにあるべき大切なことを、24年にわたって精悍に舞台を作り続けているパパ・タラフマラの小池さんはじめパフォーマーの皆さんの姿勢からひしひしと感じたのが最大の収穫だった。その行き渡った視線は劇場入りから退出まで終始貫かれていて、作品をぴりっといきいきとDANCE BOXの空間に立ち上げていった。
「三人姉妹」は、凹凸なら凸の仕掛け(Key)があらゆる所にちりばめられている印象。舞台を四角に区切るテープ、音、小道具の数々、パフォーマーの表情、動き、言葉、歌、照明などがどんどん自分の中に引っかかってくるから、(自分なりの)物語を想像しながら読んでいくような楽しみがあった。
そして、アフタートークの司会、、、小池さんに委ねながらさせてもらいました。小池さん、ありがとうございました。もしこの次があるのなら、成長した姿で挑みます。(誓)
|